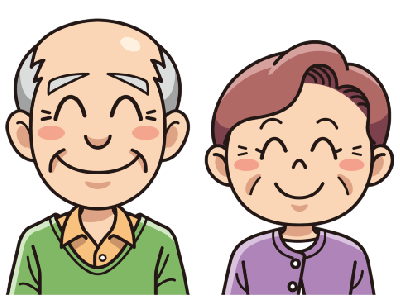子供の体と生活術

子供の健康の要は「お腹を大切にする」ことです。
中医学から見た子供の身体 子供の身体は、大人と違う大きな特徴があります。 ひとつは、内臓も組織もまだ未熟で、とてもデリケートである、ということです。でも「未熟」=「弱い」というわけではありません。 成長段階に当たるため、生命力自体はとても旺盛です。 だから、すぐ病気をしますが、そのかわり治るのも早いのです。 なお、内臓の中で、子供の病気と最も関係が深いのは、「肺」(呼吸器)、「脾」(消化器)、そして「腎」です。なかでも、食生活と最も関係が深いののは、消化器である「脾」です。 脾は、後天的なエネルギーを生み出す臓器です。肺や腎といった他の臓器も、脾が作り出すエネルギーの恩恵を受けて、成長していきます。 つまり、子供の健康の要となるのは、「お腹を大切すること」なのです。
*「脾」:中医学の考えに、五臓の一つで、食べ物を消化吸収して、身体に必要なエネルギーで ある「気」を作り出す機能があります。

冷菓ばかり食べさせない
子どもたちの食生活で、冬でも子供に冷たいジュースを飲ませたり、アイスクリームをいつも食べさせているご家庭は注意が必要です。 中医学では「冷たい食べ物のとりすぎは脾胃を傷つける」と考えています。そのため、中国の母親たちは、夏でもあまり冷たいお菓子を子どもたちんは与えません。たまの楽しみにとっておくぐらいです。 とはいえ、日本の夏は本当に蒸し暑く、上手に水分、ミネラルを補給して体の熱を外に追い出しておかないと、夏バテしたり、熱中症にかかりやすくなってしまいます。

スイカや緑豆で暑熱をとる
夏におすすめしたいのは、旬を迎える果物です。 特に、体の熱を冷まし、潤いを補う効果のあるスイカは、夏にはぴったりのおやつと言えます。 また、夏バテや日射病の予防に抜群の効果があるのが、緑豆のスープです。体の熱を冷ます作用があり、決して冷やしすぎることはありません。作り方は簡単で、2~3時間水に浸してコトコト煮るだけです。すぐに柔らかくなります。 緑豆は日本でも簡単に手に入るようになりましたので、ぜひお試しください。 なお、このスープも、室温程度に温めて飲むようにしてください。
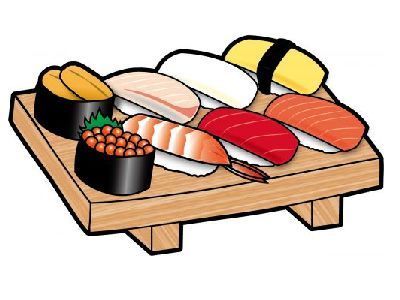
刺身などの生ものは控えめに
少し気になることは、日本ではお寿司がブームですが、子供たちまでがお寿司が大好きだということです。 まだ小学校に上がる前くらいの子供でも、美味しそうにお寿司を食べています。 しかし、中医学的には、ちょっと不安です。生もの・冷たいものと同じように、脾を傷つけます。脾は、後天的なエネルギーを生み出す大切な臓器です。脾の消化吸収能力が低下すると、後天的なエネルギーを上手く作り出すことができなくなってしまいます。 このことは、子供の発育にも影響を与えることになります。

生ものは「痰」の原因にもなる
さらに、生ものは消化に悪いので、子供の未熟な脾ではうまく処理できず身体に不必要な物質(痰など)を生み出す原因にもなります。 魚を生で食べる習慣は、日本の文化の一つだと思いますが、中医学から見ると、無条件におすすめできる食べ物ではないこと知っていてほしいと思います(特に胃腸の未熟な子どもたち)
*身体に不必要な物質とは?:身体に余分な水がたまると、痰(たん)や飲(いん)などの病気 の原因物質が生まれます。 痰は重く粘りのある性質で、飲はそれほど粘り気のないものをさしますが、両者の明確な 境界線はないため、痰飲(たんいん)、痰湿(たんしつ)、水飲(すいいん)などと呼ばれてい ます。これらの物質が生まれると、胃腸の機能障害が起こり、気や血などが十分に作り出 されなくなる原因にもなります。
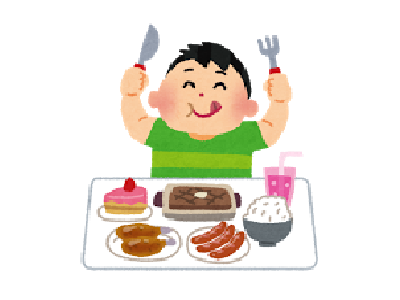
エアコンの使い過ぎに注意
親というものは、子供が食べないことは気に病んでも、食べ過ぎは案外気にしなかったりするものです。 食欲は健康状態のバロメーターでもあるので「食べられているようなら、安心」と思う気持ちもよくわかります。 でも、消化器が未熟な子供にとって、大敵なのは飽食。中医学では子供は、「三分の飢え」、つまり腹七分目が良いとされています。 食べさせすぎることのないよう、十分に気を付けてください。また「今日はあまりご飯を食べなかったから、せめておやつでも」と、スナック菓子や甘いものを与えているお母さんをよく見かけますが、これは逆効果。 食べない子には、無理に食べさせようとせず、むしろおやつを抜いて、外でたくさん遊ばせ、うんとお腹がすくように仕向けてください。普段は遊び食いしかしないような子でも、真剣にご飯を食べるようになるはずです。 おやつは、2~3歳までの子にとって補食の意味もありますが、脂肪分や糖分の多いお菓子を毎日与えるのは決して良い習慣とはいえません。そういうお菓子は、たまの楽しみにとっておいて、普段は、豆を煮たものや芋をふかしたものなど、素朴なおやつを上げるようにしたいものです。

エアコンの使い過ぎに注意
子供の病気の中で、最も多いのは、やはり風邪。 2~3日で完全に治ってしまうような風邪なら、どんどんひいて、免疫をつけることも大切ですが、長引いたり、こじれたりすると、体力が落ちてしまい、他の病気を併発しやすくなりますし、薬づけになる一因にもなってしまいます。 風邪をひかない子供にすためには、まず、環境を整えるのが大切です。たとえば、エアコン。寒い季節は、風邪をひかないようにと、つい温度を高く設定してしまいがちですが、外気との気温差が大きすぎると、かえって風邪をひきやすくなります。 中医学では、子供には「三分の飢え」と同じくらい「三分の寒」も大切だと考えています。 寒といっても、わざわざ薄着にしたり、冷たいものを食べさせる、というわけではありません。子供は新陳代謝が激しいので、厚着をさせないほうがいい、というくらいの意味です。 現代生活でも、最も「三分の寒」に反すると思われるのは、やはりきつすぎる暖房だと思います。特に、デパートや電車の中の暖房は、半袖でもいいくらいの温度設定になっていて、冬でも汗をかいてしまうことがあります。そのまま寒い外に出ると、それこそ風邪の原因になりますので、衣服で調節してあげましょう。 同じく夏の冷房も風邪のもと。春夏秋冬を通して、できるだけ自然に近い生活を送ることで、皮膚も鍛えられ、ひいては「肺」も丈夫になり、風邪もひきにくくなっていくのです。
*肺と皮膚:中医学では、肺と皮膚はは密接な関係があると考えられています。肺は体の防衛力である衛気(えいき)を全身にめぐらせているため、肺の機能が正常働いていると、外界から病気の原因となるウイルスなどの物質の侵入を防ぐことができます。衛気は、体の表面を流れている体の防衛機能の最前線といえます。
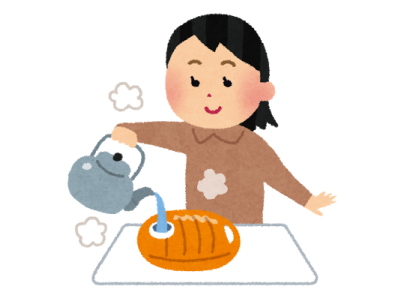
背中とお腹と足は温めて
子供に厚着は必要はありませんが、内臓を冷やすのは良くありません。もっとも冷やしていけないのが、お腹です。冷たい食べ物を避けるんぼはもちろん、外からの冷えにも気をつけなてはいけません。 暑い季節でも、お腹が出ないような服装を心がけてください。寝るときは、腹巻をするのもお勧めです。 また、背中には内臓につながる「ツボ」が集中しています。そこを冷やすことは、内臓を直接冷やすことにつながります。 もう一つ、足も冷えから守ることが大切です。日本では、冬でも半ズボンで過ごしている子供が多いようですが、中医学的には、あまりお勧めできることではありません。 足を冷やすと、風邪をひきやすくなってしまいますので、足の保温に努めるように工夫してほしいものです。
*ツボ:中医学では、体の体表面には経絡(けいらく)という道筋があると考えられています。経絡は全身に体のエネルギー源である気や、栄養分である血を運ぶ道筋で、身体の生理機能である五臓と皮膚をつないでいます。
その他メニューのご紹介
見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。
見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。
見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。